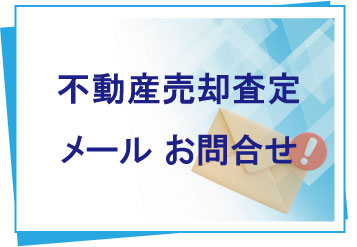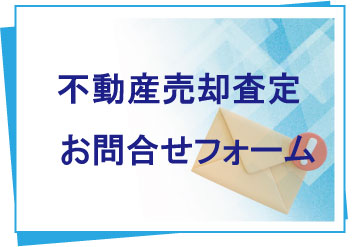区分所有法改正

2025年5月に成立して、2026年4月から施行される「建物の区分所有等に関する法律」(以下「区分所有法」)が大きく改正されます。今回の改正は、老朽化マンションの増加や所有者不明問題、災害時の再建困難など、現代のマンションが抱える深刻な課題に対応するためのものです。

その改正される中の一つに、集会決議の要件が一部緩和されて、総会などの集会の出席者の過半数で決議できることになりました。ということは、管理組合の総会に出席しなければ、勝手に管理費・修繕積立金を上げられてしまう、という恐れが出てきたということでしょうか。
「総会出席者の過半数」で管理費が勝手に上がる?区分所有法改正の実態
2026年4月に施行される区分所有法の改正では、マンション管理に関する集会決議の要件が一部緩和され、「総会出席者の過半数」で決議できる範囲が広がります。これにより、無関心な所有者の存在によって意思決定が滞る事態を回避できると期待されています。しかし一方で、「総会に出席した人だけで管理費や修繕積立金を勝手に上げられてしまうのでは?」という懸念も聞かれます。この疑問に対して、制度の仕組みと実務上の制約を整理しながら、誤解を解いていきましょう。
管理費変更は「普通決議」ですが、定足数が必要
まず、管理費の金額変更は「普通決議」に該当します。これは、区分所有者の議決権の過半数で可決される決議方式です。改正後は「出席者の過半数」で決議可能となる場面が増えますが、これはあくまで「定足数を満たしたうえでの出席者による多数決」です。つまり、総会が成立するには「議決権総数の過半数の出席」が必要であり、出席者が極端に少ない場合はそもそも決議自体が無効となり、出席者だけで好き勝手に決められるわけではありません。

「勝手に上げる」は制度上できない理由
懸念される「勝手な値上げ」が制度上できない理由は、以下の通りです。
① 管理規約に基づく運用が必須
多くのマンションでは、管理費の算定方法や変更手続きが管理規約に明記されています。この規約に従わない変更は、たとえ決議されたとしても無効とされる可能性があります。
② 総会での議案提示と説明義務
管理費変更は、総会の議案として事前に各組合員に通知される必要があります。議案書に記載されていない内容を突然総会で提案し、決議することは原則として認められていません。区分所有者が事前に内容を把握できるよう、透明性が求められます。
③ 住民の信頼と合意形成が不可欠
法的には決議可能でも、組合員の納得なしに強行すればトラブルの火種になります。説明会やアンケートなどを通じて、合意形成の努力が不可欠です。管理組合の運営は、法令だけでなく組合員の信頼によって成り立っています。
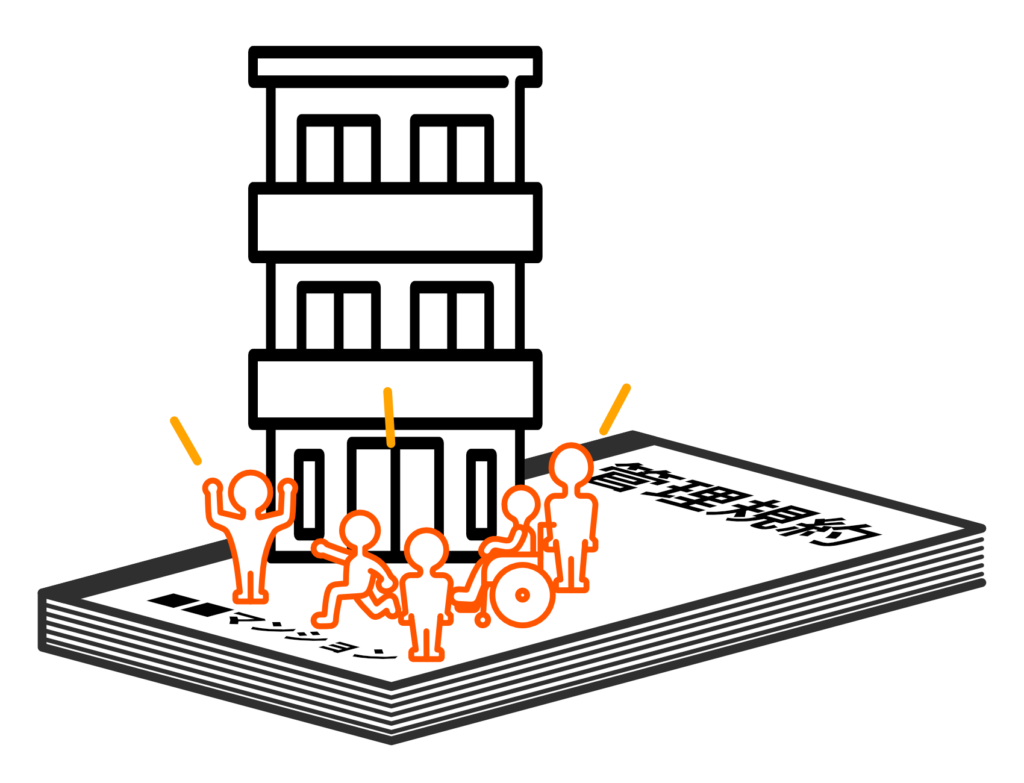
「決議要件の緩和」は、あくまで意思決定の円滑化を目的とした制度です。乱用すれば信頼を損なうことになりかねません。制度の趣旨を正しく理解し、区分所有者との対話を重ねることが、健全なマンション管理の第一歩です。
お子様へ贈る 今月のおすすめ絵本(読物)

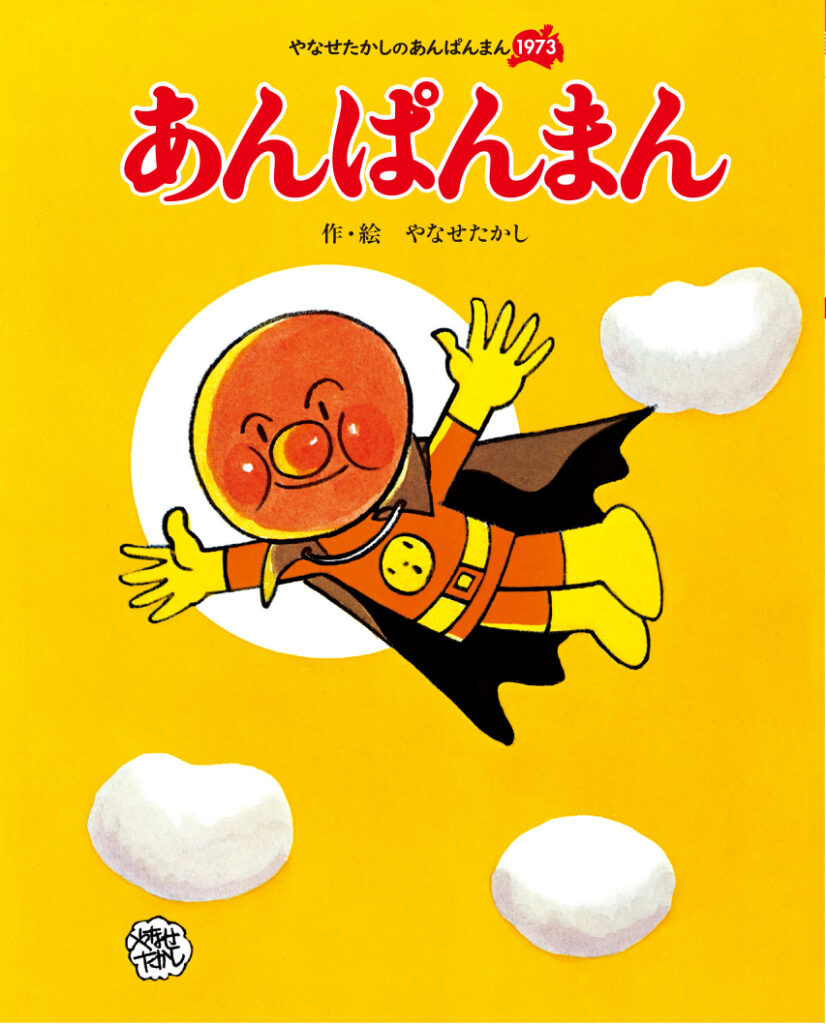
あんぱんまん
作・絵:やなせ たかし
出版社:株式会社フレーベル館
一人の旅人がお腹を空かして今にも死にそうになっていた時、大きな鳥のようなものが近づいてきました。【さぁ、僕の顔を食べなさい。僕の顔はとびきり美味しい】旅人はおそるおそるあんぱんまんの頭にかじりつきました。その美味しいことはびっくりするぐらいでした。
トウリハウジング特選物件情報
編集後記

その他の区分所有法改正の要点まとめ
2025年の区分所有法改正では、集会決議の要件緩和以外にも、マンション管理の現場に大きな影響を与える制度変更が多数盛り込まれています。以下に、特に重要な改正ポイントを簡単にまとめました。
① 所有者不明住戸への対応強化
所在不明の区分所有者がいる場合、裁判所の判断によりその議決権を除外できる制度が創設されました。これにより、修繕や建て替えなどの合意形成が柔軟に行えるようになります。
② 建て替え・一括売却の要件緩和
耐震性不足や老朽化が認められる場合、建て替え決議の要件が組合員の「5分の4」から「4分の3」に緩和されました。また、敷地売却や建物更新も多数決で進められる制度が導入され、再生の選択肢が広がります。
③ 管理不全への対処制度
理事会の機能不全や管理費滞納など、管理不全状態にあるマンションに対しては、裁判所が「管理人」を選任し、第三者による管理介入が可能となりました。これにより、放置された住戸や共用部の改善が期待されます。
④ 国内管理人制度の新設
国外居住の区分所有者に対しては、国内に居住する代理管理人の選任が義務付けられるようになりました。管理組合との連携が円滑になり、合意形成や規約改正が進めやすくなります。
これらの改正は、老朽化・高齢化・所有者不明といった現代のマンションが抱える課題に対する、制度的な処方箋です。管理組合としては、規約の見直しや台帳整備、専門家との連携を通じて、改正をチャンスに変える準備が求められます。